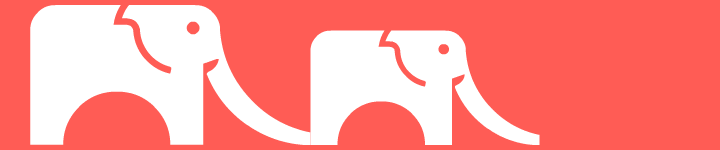厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準」は、国民の健康維持や生活習慣病の予防を目的とした、栄養摂取のガイドラインです。2025年版では、超高齢社会の進行や生活習慣病の増加といった社会的背景に対応し、より実践的かつ生活に活かしやすい内容へと見直されました。
今回はその中から、特に注目すべきアップデートポイントをご紹介します。
今回の改定で、何を目指したのか?
今回の改定は、以下のような明確な健康課題に対応するために行われました。
- 健康寿命が平均寿命よりも約10年短いこと
- 高齢者の筋力低下や転倒が、介護の主な要因となっていること
- 若い世代にも生活習慣病のリスクが広がっていること
- 栄養摂取状況に個人差が大きく、基準とのギャップが見られること
こうした課題をふまえ、2025年版では以下のような改定が行われています。
主なアップデートポイント
食物繊維の目標量引き上げ
2020年版では:
成人男性21g/日、成人女性18g/日が目標量とされていた。2025年版では:
成人男性25g/日以上、成人女性20g/日以上に引き上げられた。その理由は:
腸内環境の改善や便通の改善に加え、循環器疾患や2型糖尿病の予防に有効であるという科学的根拠が蓄積されたため。複数の研究により、1日25g以上の摂取が健康効果に寄与すると評価されるようになったため。
ビタミンDの「目安量」が新たに設定
2020年版では:
成人(18歳以上)のビタミンDの目安量(AI)は、男女ともに 8.5μg/日 と設定さいれていた。2025年版では:
成人男女ともにビタミンDの目安量が9.0μg/日に引き上げられた。その理由は:
日本人のビタミンD摂取実態が少なく、骨粗しょう症やフレイル対策の観点から摂取の重要性が高まったため。骨の健康維持に不可欠であることが再認識された。
鉄の「耐容上限量(UL)」が削除
2020年版では:
成人男性45mg/日、成人女性40mg/日の耐容上限量が設定されていた。2025年版では:
鉄の耐容上限量の設定が削除された。その理由は:
通常の食品からの鉄摂取では過剰摂取による健康被害のリスクが低いと判断されたため。科学的根拠が限定的で、安全上限値として示す意義が乏しいとされた。
身体活動レベルの表記がわかりやすく変更
2020年版では:
身体活動レベルはレベルⅠ(低い)、Ⅱ(ふつう)、Ⅲ(高い)とローマ数字で表記されていた。2025年版では:
「低い」「普通」「高い」と、平易な言葉での表記に変更された。その理由は:
ローマ数字表記が誤解を招きやすかったことから、より直感的に理解できる表記に変更されたため。
アルコールの扱いが独立項目に
2020年版では:
アルコールは「炭水化物」の一部として扱われていた。2025年版では:
アルコールは「エネルギー産生栄養素」として独立項目に位置づけられた。その理由は:
アルコールは炭水化物とは化学的・栄養学的に異なる物質であり、エネルギー源として分類する方が合理的と判断されたため。
「骨粗しょう症」「フレイル」への対応が強化
2020年版では:
フレイルや骨粗しょう症は、明確に対象とはされていなかった。2025年版では:
これら疾患の予防・改善の観点から、関連栄養素(ビタミンD・カルシウム・たんぱく質など)の記載が拡充された。その理由は:
超高齢社会を見据え、高齢者の身体機能維持・転倒予防といった観点から、栄養管理の重要性が高まっている。こうした背景を受けて、2025年版ではビタミンDやカルシウム、たんぱく質との関連が強調され、対応強化が必要になったため、該当項目の記載が拡充された。
推定エネルギー必要量の表示は実態に即した参考値へ
2020年版では:
性・年齢・身体活動レベル別の推定エネルギー必要量が「表形式で提示されていた」が、参考値であることの強調は弱かった。2025年版では:
「参考表」としての位置づけがより明確になり、個人差が大きいことを踏まえて活用することが推奨されている。その理由は:
エネルギー必要量には個人差が大きいことから、一律の数値を示すのではなく、目安としての参考値を用いることが適切と判断されたため。
エビデンスレベルの明示(目標量)
2020年版では:
エビデンスレベルの明示はなかった。2025年版では:
目標量に関して、科学的根拠の強さをD1〜D5で分類するエビデンスレベルが示された。その理由は:
栄養素ごとの信頼性を把握しやすくすることで、実務における活用性を高める必要があると判断されたため。特に、生活習慣病予防を目的とした目標量の設定や活用において、エビデンスレベルの明示が有効であると考えられたため。
まとめ
今回の改定は、「平均寿命は延びたが、健康寿命とのギャップが埋まらない」「フレイルや骨粗しょう症といった高齢者の課題が深刻化している」「生活習慣病の若年化や重症化が進んでいる」といった現代の健康課題に真正面から向き合ったものです。
高齢者の自立支援に不可欠な骨や筋肉の維持、食の嗜好や実態に寄り添った現実的な指標設定、そして科学的根拠に基づいた生活習慣病予防の強化——。
これら「予防」「実行」「根拠」の3つを軸に据えた、より実践的な栄養基準へのアップデートになっていると思います。
私たちは、民間企業として、商品やサービスを通じて栄養と健康を“日常の中”に届けることができます。医療や行政では届きにくい場所にこそ、私たちの選択とものづくりが生きる場があります。
一つひとつの栄養素が示す意味と、背景にある社会課題を理解したうえで、この基準を活かした商品づくりや情報発信を積み重ねていくこと。それが、企業として“健康寿命を延ばす社会づくり”に貢献する一歩だと考えています。
この改定をきっかけに、私たち自身の取り組み、商品の栄養価設計を見直し、社会に必要とされる「本当に意味のある食と健康の提供」に尽力していきたいと思います。